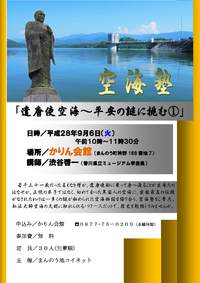2008年02月12日
満濃池と讃岐の水事情

讃岐の水を語るとき、よく「水との闘い」という言葉が使われる。それは水を求めてのたゆまざる努力を意味している。一万四千六百余の溜池の築造は、先人が現代に残した尊い遺産である。亦永い水利史のなかで培われ定着した水利慣行も、水との闘いの証である。水利慣行はややもすれば悪者扱いされがちであるが、必ずしもそうではなく、水についての慣行行事のなかには、水に対する感謝と敬虔な祈りすら組み込まれている。

讃岐では古来から雨乞いの行事がしばしば行われており、古くは仁和四年(888)の旱魃に、時の讃岐の国守 菅原道真が、城山で七日七夜雨乞いしたと言う古事に始まり、法然上人による念仏踊りなど枚挙にいとまがない。
雨乞いは昭和に入ってからも様々な形で行われ、昭和九年の旱魃時には、県知事が祈雨の応急対策として、善通寺師団に山砲による実弾発砲を要請し、山砲十二門で二百余発の射撃を行った(八月二十九日)ほか、各市町村に対して「八月三十日から三日間、篝火を焚き一斉に雨乞いせよ」との通達を出したりしている。また昭和十四年の大旱魃でも市町村へ雨乞い祈願の実施と、学童に朝夕土瓶で稲株一株毎に水をかける「どびん水」を実施するよう通達したりしている。今日からみると非科学的と一笑されることではあるが、讃岐の先人たちの水に対する必死の思いと、切実な祈りの姿を見ることができる。
ところで善通寺師団の実弾発砲の効果であるが皮肉なことに阿讃山脈を隔てた徳島県池田で大雨が降り、早速池田の代表者がお神酒を提げて、善通寺師団司令部にお礼言上に来たという笑えない話がのこっている。念のため真偽の程を徳島地方気象台に電話で確認したところ昭和九年八月二十九日に四・二ミリ、翌三十日に四九・九ミリ降っていました。
Posted by まんのう池コイネット at 06:49│Comments(2)
│満濃池の歴史・史跡
この記事へのコメント
コメントありがとうございました。
私は満濃池は一度だけ行ったことがあります。
若いころ(今も若いですが・・・)。
雪の満の池きれいですね!
私は満濃池は一度だけ行ったことがあります。
若いころ(今も若いですが・・・)。
雪の満の池きれいですね!
Posted by 豊葛(とよかつ) at 2008年02月12日 08:43
>豊葛さま わざわざのお越しありがとうございます。 若い頃ですかぁ~プロフィールを見ると私より遥かにお若いですね
満濃池は一年中綺麗ですよ 一度といわず何度でも起こし下さい。
満濃池は一年中綺麗ですよ 一度といわず何度でも起こし下さい。
Posted by まんのう池コイネット at 2008年02月12日 18:08
at 2008年02月12日 18:08
 at 2008年02月12日 18:08
at 2008年02月12日 18:08