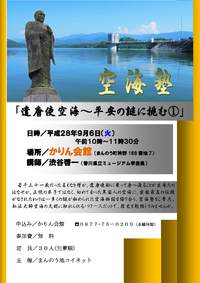2008年05月19日
満濃池人物伝 長谷川喜平次・佐太郎
長谷川 喜平次
満濃池の底樋は当時木製で二、三十年に一回は伏替を余儀なくされていた。
この普請は農家にとっては大きな負担であった。これを軽減しようと考えたの
が那珂郡榎井村の里正(庄屋)長谷川喜平次であった。
嘉永二年(1849)農民の苦労と不経済さを勘案して半永久的に伏替を必要と
しない石造りにしてはと考え、高松、丸亀藩両藩の了解を得て庵治石で底樋を
作ったのである。これに必要な莫大な工費には、喜平次自身も数千両の私財を
投じたと言われている・其のお蔭で工事は嘉永二年八月に着工、翌年四月には
底樋の前半部を石製に改修、喜平次はこの完成に自信を持ち、嘉永五年八月後
半部工事に着工、翌六年四月には全工事が完成した。
ところが巨大な池だけに水圧が大きく、嘉永七年七月六日朝、石造底樋より
水が浸潤しているのを池守が見つけ、高松 丸亀藩から担当者が出て農民も総
出で応急工事に当たったが漏水が止まらず、事態は最悪となり、九日ついに決
壊する。
高松藩記によると 六月十四日地震、七月九日満濃池決壊 とある。のでこ
の決壊は地震によるものであったのかもしれないが、当時すでに田植えも終わ
っており、貯水は10パーセント程度しか残っていなかったがこの水で池下の村
の田畑は流され死傷者が続出し、金蔵川は溢れ返り琴平で冠水60センチとの
記録が残っている。
最も悲嘆に暮れたのは底樋石造を総指揮した庄屋の喜平次であった。
喜平次は名を信直、字を帰中と言い、通称倉敷屋喜平次と呼び、俳句にも才
を発揮し雨艇と号した粋人あったという。
その後十数年、この地一帯は池なし村となりこの時代不思議と旱魃と洪水が
繰り返され、その受難の最中、喜平次は失意のまま文久二年(1862)六十七才の
生涯を閉じた。
喜平次の死後、何十回にも及ぶ協議の末、明治になってからやっと再築が
実現する。
その遺志を受け継いだのは、同村の豪農長谷川佐太郎であった。
長谷川翁功徳之碑

満濃池堤防東詰めに一際大きく立派な石碑が聳え建っています。
この碑は長谷川佐太郎の功績を讃え、明治の元勲山縣有朋が題字、子爵品川
彌二郎の撰文、衣笠豪谷の書により、明治二十九年十一月、朝廷より翁の功を賞し、藍綬褒章及び金五十円を賜るを機に建立したもであります。
碑文には、こころざしを道とし、よりどころを徳とし、人の道理を基本に、遊びを芸とすることは、おそらく長谷川翁のいうところである。・・より始まり翁の功績が事細かく列記され、最後に、世間の評判や立身出世を待たなかった翁は、生まれつきの徳に由来する大宗師といえよう。と記している。
安政元年決壊した満濃池は、水掛りが、高松、丸亀、多度津の三藩にまたがり、天領も含まれていて、復旧には各藩と倉敷代官所の合意が必要で、意見の一致が得られないまま十六年放置されていた。
長谷川佐太郎は、この間、満濃池の復旧をうったえて奔走するも、目的は果たせず幕府は崩壊する。彼は好機到来とばかり、勤皇の同志を頼って上京し、新政府に百姓の苦難を切々と訴え、早期復旧の嘆願書を提出し、明治二年着工同三年に竣工した。この間彼は一万二千両に及ぶ私財を投入し、晩年には家屋敷も失い清貧に甘んじている。
長谷川佐太郎石碑場所は
満濃池の底樋は当時木製で二、三十年に一回は伏替を余儀なくされていた。
この普請は農家にとっては大きな負担であった。これを軽減しようと考えたの
が那珂郡榎井村の里正(庄屋)長谷川喜平次であった。
嘉永二年(1849)農民の苦労と不経済さを勘案して半永久的に伏替を必要と
しない石造りにしてはと考え、高松、丸亀藩両藩の了解を得て庵治石で底樋を
作ったのである。これに必要な莫大な工費には、喜平次自身も数千両の私財を
投じたと言われている・其のお蔭で工事は嘉永二年八月に着工、翌年四月には
底樋の前半部を石製に改修、喜平次はこの完成に自信を持ち、嘉永五年八月後
半部工事に着工、翌六年四月には全工事が完成した。
ところが巨大な池だけに水圧が大きく、嘉永七年七月六日朝、石造底樋より
水が浸潤しているのを池守が見つけ、高松 丸亀藩から担当者が出て農民も総
出で応急工事に当たったが漏水が止まらず、事態は最悪となり、九日ついに決
壊する。
高松藩記によると 六月十四日地震、七月九日満濃池決壊 とある。のでこ
の決壊は地震によるものであったのかもしれないが、当時すでに田植えも終わ
っており、貯水は10パーセント程度しか残っていなかったがこの水で池下の村
の田畑は流され死傷者が続出し、金蔵川は溢れ返り琴平で冠水60センチとの
記録が残っている。
最も悲嘆に暮れたのは底樋石造を総指揮した庄屋の喜平次であった。
喜平次は名を信直、字を帰中と言い、通称倉敷屋喜平次と呼び、俳句にも才
を発揮し雨艇と号した粋人あったという。
その後十数年、この地一帯は池なし村となりこの時代不思議と旱魃と洪水が
繰り返され、その受難の最中、喜平次は失意のまま文久二年(1862)六十七才の
生涯を閉じた。
喜平次の死後、何十回にも及ぶ協議の末、明治になってからやっと再築が
実現する。
その遺志を受け継いだのは、同村の豪農長谷川佐太郎であった。
長谷川翁功徳之碑

満濃池堤防東詰めに一際大きく立派な石碑が聳え建っています。
この碑は長谷川佐太郎の功績を讃え、明治の元勲山縣有朋が題字、子爵品川
彌二郎の撰文、衣笠豪谷の書により、明治二十九年十一月、朝廷より翁の功を賞し、藍綬褒章及び金五十円を賜るを機に建立したもであります。
碑文には、こころざしを道とし、よりどころを徳とし、人の道理を基本に、遊びを芸とすることは、おそらく長谷川翁のいうところである。・・より始まり翁の功績が事細かく列記され、最後に、世間の評判や立身出世を待たなかった翁は、生まれつきの徳に由来する大宗師といえよう。と記している。
安政元年決壊した満濃池は、水掛りが、高松、丸亀、多度津の三藩にまたがり、天領も含まれていて、復旧には各藩と倉敷代官所の合意が必要で、意見の一致が得られないまま十六年放置されていた。
長谷川佐太郎は、この間、満濃池の復旧をうったえて奔走するも、目的は果たせず幕府は崩壊する。彼は好機到来とばかり、勤皇の同志を頼って上京し、新政府に百姓の苦難を切々と訴え、早期復旧の嘆願書を提出し、明治二年着工同三年に竣工した。この間彼は一万二千両に及ぶ私財を投入し、晩年には家屋敷も失い清貧に甘んじている。
長谷川佐太郎石碑場所は
Posted by まんのう池コイネット at 14:18│Comments(0)
│満濃池の歴史・史跡