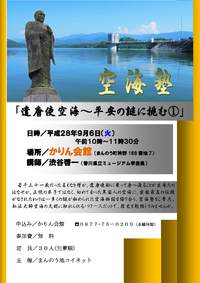2008年08月20日
弘法大師再築の特徴 その2

第二は洪水時の堤防破壊を防ぐ目的で岩盤を開削し、余水吐(うてめ)を設けた。その際水の突き当たる堤防の西南端の岩盤を掘り下げて余水吐の幅と高さを決めている。この余水吐は岩の表面が大工道具の手斧で削ったようになっていたため、後に弘法大師の「お手斧岩(おちょうないわ)」と呼ばれるようになった。それまでは池に余水吐がなく大雨の時にはゆる抜きをして水を放水していたため、堤防の決壊が危ぶまれることが多々あったが弘法大師は余水吐の設置で堤防の安全をはかったのである。この余水吐は昭和五年の第二次嵩上げ工事で堤防内に埋没した
埋没したお手斧(おちょうな)岩付近

現在の余水吐です

弘法大師のお手斧岩(おちょうないわ)のあった付近↓
Posted by まんのう池コイネット at 15:31│Comments(0)
│満濃池の歴史・史跡