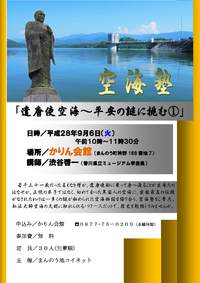2008年02月16日
満濃池がその昔赤レンガの配水塔だった頃

大正三年(1914)の師走、満濃池に赤レンガ造りの配水塔が出現した。円筒形に赤レンガを積み上げ、六角錐の屋根をつけた姿は、溜池王国香川が全国に誇れるモダンな景観であった。
幕末に決壊した満濃池は明治三年に復旧されたが、このとき従来の木造の底樋は廃止し、池底の岩盤にトンネルを抜いて石穴底樋とした。しかし石穴と斜樋、取水櫓などは従来どうり木造であった。そのため僅か三十年足らずで腐食し、明治三十一年には斜樋管の取替えをおこなっている。
当時 満濃池普通水利組合の管理者であった乾貢は取水施設を視察し、前任地愛知県の入鹿池の取水塔方式を提案した。組合総代達も恒久施設の必要性を痛感し、新方式の導入の検討を開始した。
この時、組合内部で水利慣行(樋外五十石、証文水)が消滅するとのことで反対する者も多数いたが、旧来の水利慣行は存続させる旨議事録に書き残すことで説得し、配水塔建設は可決された。
工事は大正三年(1914)九月に着工、総工費一万八千九百二十一円五十五銭
同年十一月に竣工した。全高六十五フイト(19,7メートル)、円筒形底部径
二十四フイト(7,3メートル)、上部径十五フイト(4,6メートル)、
その構造外観を大正七年刊行の仲多度郡史より引用すると
自然岩を基底とし、コンクリートと花崗岩を布置してその基礎を造り、レンガを重畳し鉄板をもって屋根とす。その構造円筒形にして・・・(中略)
内部中央に直立する鉄管あり。石穴の一端に接続す。吸入鉄管総数七個あり。上下適当な位置に配置して中央の立管に接続す。しかして各吸入鉄管に止水弁を備え、上部の屋内に備えたる スタンドポスト 称する小機によりて開閉を自由ならしむ。その機能と軽快な放水調節は、じつに完備というべし。と絶賛している。
なにしろ大正初年といえば、農村工事ではまだコンクリートやモルタルレンガ積みが珍しく、ましてや配水塔に鉄管を配置しバルブ操作で配水する等、当時としては画期的な設備であった。
現在の配水塔

Posted by まんのう池コイネット at 06:32│Comments(0)
│満濃池の歴史・史跡