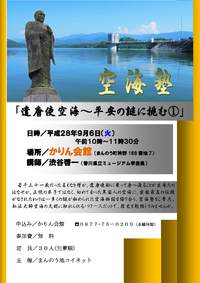2008年03月07日
空海が池修築の安全を祈願した護摩壇岩

満濃池は弘仁九年の洪水で決壊し、築池使 路ノ真人浜継が再築に着手するも一向に進まず、国守の嘆願で嵯峨天皇の命を受け、弘仁十二年空海(弘法大師)が築池別当として派遣され、再築された話は有名ですが、その時空海は池東の堤防が見渡せる高台岩上に、護摩壇を作り工事期間中護摩を焚き、工事の無事完成を祈ったと伝えられ、その岩山は今も護摩壇岩として残っています。写真は堤防東(現在)から中央の松林の中にある護摩壇岩そして遠くに見えるのが配水塔です。
空海再築の昔から大正時代までは(池が決壊し池内に村が出来た時期を除いて)、満濃池はこの護摩壇岩下が堤防の東詰めであり、そこから西側までの堤防が昭和の嵩上げまでは使われていたようです。
今ちょうど水位が下がり昭和初期まで使われていた旧堤防が顔を覗かせていました。歴史の中で幾度も形を変えてきた満濃池ですが現在の姿は西嶋ハ兵衛の築造した池が原形であると言えるのではないかと思われます。
↓写真は昭和(撮影年月日不明)の嵩上げ頃の対岸付近から写した護摩壇(中央の茂み・このころは樹木も沢山あったようです)と現在の堤防嵩上げ工事の進捗具合をとったもののようです。

Posted by まんのう池コイネット at 09:37│Comments(0)
│満濃池の歴史・史跡