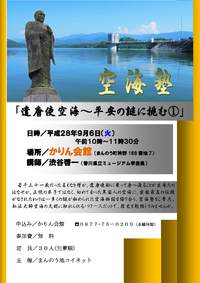2008年06月23日
満濃池の創築

上 萬農池後碑文
当地讃岐は大陸や朝鮮半島の文化の影響を受けて早くから開拓され、とくに大和と吉備の二つの文化圏に近い丸亀平野は稲作の重要拠点の一つであった。八世紀になると河道沿いの低地や湧水知に小さなため池が築かれていたであろうことは想像できる。
満濃池創築は、古文書「讃岐国萬農池後碑文(さぬきくにまんのういけのちのひぶみ)」によると「此の池は大宝年中 国守道守朝臣(みちのもりのあそん)の築く所なり」と書かれている。ただ、この石碑は大宝年間より三百年も後の寛仁四年(1020年)に建立されたもので、その石碑も現存せず、碑文のみが名古屋市中区大須二丁目の真福寺に所蔵されている。
当時大和朝廷は大化の改新を断行し、ようやくその基礎を固め、国司、郡司を直接指揮し、全国に水田の開発に乗り出してたという時代背景から考えて、満濃池の創築が大宝年間(701年~704年)讃岐の国守 道守朝臣によるものとすると今から凡そ1305年前のこととなる。
Posted by まんのう池コイネット at 07:00│Comments(0)
│満濃池の歴史・史跡